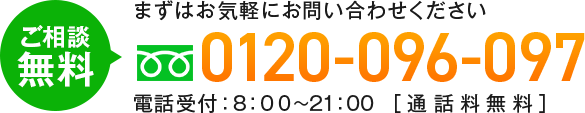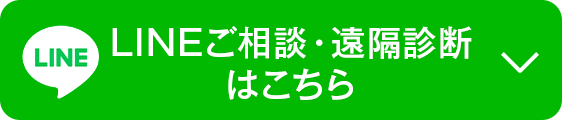密閉式暖房ボイラーの適正圧力とは?正常な圧力変化と異常の見分け方を解説
「暖房ボイラーの圧力って、どれくらいが正常なんだろう?」
「運転中に圧力が上下するけど、大丈夫なのかな…」
密閉式暖房ボイラーを使用していると、こんな疑問を感じる方は少なくありません。
特に、運転中に圧力が上がったり下がったりする現象は、故障なのか正常な動作なのか判断がつきにくいものです。
この記事では、密閉式暖房ボイラーにおける適正な圧力の目安から、運転のON/OFFによる一般的な圧力挙動、そして構造や配管接続の違いによって現れる正常なケースのバリエーションまで、順を追ってわかりやすく解説します。
さらに、「実は異常だった」という故障が疑われる圧力挙動の見分け方もお伝えします。
不要な出費やトラブルを避けて、落ち着いて対応するためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。
密閉式暖房ボイラーの「適正圧力」
一般家庭や小規模施設にみられる密閉式の暖房用温水ボイラーでは、システム内の圧力が0.01〜0.1MPa程度に保たれていることが、安全で安定した運転の基本です。
この圧力範囲は、法令上「小型ボイラー」として扱うための制限にも関係しています。
圧力が0.1MPaを超えると「高圧ボイラー」として法的な規制対象となるため、メーカー側でも設計上の上限が0.1MPa未満に設定されていることが多いです。
一方、中規模・大型施設では、0.1MPaを超える高圧型の温水ボイラーや、蒸気ボイラーが導入されていることもあります。
これらの機種は加熱時に0.2〜0.5MPa程度の圧力で運転されることがあり、運転監視や安全弁の仕様も小型ボイラーとは異なります。
そのため、施設に導入されているボイラーの種類(温水式/蒸気式)や設計圧力の上限を、必ずメーカー仕様書などで確認することが重要です。
なお、より細かく判断したい場合は、停止時の圧力がどれくらいかを見るようにしましょう。
小型ボイラーや密閉式の温水循環回路では、停止時(=水が加熱されていない常温時)における初期圧力を基準に挙動をみて、「正常かどうか」を判断します。
適正圧力は、実際のところはシステム設計や機種、圧力計の取り付け位置によって異なるため、停止時の圧力から挙動をみていくと、より正確に異常の有無が判断できます。
圧力は「運転ONで上昇/運転OFFで低下」が基本
暖房ボイラーの圧力は、運転ONで圧力が上がり、OFFで下がるのが正常な挙動です。
これは、水が加熱されて膨張する物理的な性質に基づいています。
たとえば、冷えている状態では0.05MPa程度だった圧力が、運転を開始すると徐々に0.1MPa近くまで上がっていくことがあります。
これは異常ではなく、温度の上昇にともなう自然な圧力変化です。
逆に、暖房を切った直後や夜間など長時間運転をしていないときは、水温の低下により圧力が元の水準に戻っていくため、圧力が低下していきます。
ただし、ボイラーの構造や接続されている配管系統の仕様によっては、圧力計の動きに多少のズレや特徴が見られることもあります。
圧力計の接続位置(計測ポイント)によっては圧力の挙動が逆になる
密閉式の暖房用温水ボイラーでは、通常「運転ONで圧力上昇、運転OFFで圧力降下」というのが基本的な圧力の変化です。
しかし、圧力計の取り付け位置(計測ポイント)によっては、運転中に圧力が下がり、停止中に圧力が上がるといった“逆の動き”を見せることがあります。
これは構造的な要因によるもので、異常とは限りません。
圧力計が循環ポンプの吸い込み口側に設置されているケース
逆表示の挙動の一例として、圧力計が「循環ポンプの吸い込み口側」に設置されているケースが挙げられます。
通常、循環ポンプが運転すると、ポンプからの圧力によって配管内に「押し出す力(正圧・吐き出し側)」と「吸い込む力(負圧・吸い込み側)」の差が生まれます。
もし圧力計が循環ポンプの吸い込み側にある場合、ポンプが動くと一時的に水が引っ張られ、圧力が下がって見えることがあります。
これに対し、ポンプが止まると水の動きがなくなり、通常保持されている圧力がそのまま配管内に反映され、圧力計の数値が上がるように見えるのです。
つまり、「運転ONで圧力が下がる」「運転OFF(停止)で圧力が上がる(戻る)」という現象がおきます。
これは、圧力の見え方が変化しているだけで、水量や圧力自体に異常があるわけではありません。
故障が疑われる圧力変化や症状例
ただし、以下のような状態は異常とみなされ、点検や修理が必要です
小型ボイラーの圧力が上がり続ける
小型ボイラー運転中に圧力が0.1MPa以上に達し、さらに上昇し続ける場合は、異常が疑われます。
さきに述べたように、法令上「小型ボイラー」として扱うための圧力上限は0.1Mpaとなっています。
そのため、0.1Mpaを超えて圧力が上がり続ける場合は、注意が必要です。
圧力が上がり続けるとき、例えば次のような原因が考えられます。
原因例
・膨張タンクのエア不足
・膨張タンクのダイアフラム(ゴム膜)の破損
膨張タンクは、配管内の上昇圧力を吸収し、配管の破裂を防ぐ役割があります。
圧力が上がり続けるということは、膨張タンクがうまく機能せず、うまく圧力が吸収できていないことが疑われます。
膨張タンクが機能せず圧力が上昇し続けると、やがて配管の破裂をまねくため、安全措置として安全弁が稼働します。
もし「安全弁から液が噴き出す」という症状を併発している場合は、膨張タンクが機能せず、安全弁が作動した可能性があります。
膨張タンクの不具合の内容については、単にエア不足のこともあれば、ダイアフラムというゴム膜が破れているときもあります。
エア不足の場合は、空気を注入すれば正常に戻ることもありますが、ダイアフラムの破損の場合は取り替えが必要です。
小型ボイラーの圧力が上がらない
逆に、ボイラーを運転しても圧力が上がらない、あるいは圧力が徐々に下がっていくといった症状も、不具合の兆候の可能性があります。
圧力が上がらないとき、例えば次のような原因が考えられます。
原因例
・配管や接続部からの不凍液漏れ
・圧力計や圧力センサーの故障
密閉回路である配管では、内部に一定量の不凍液(または温水)が充満しており、その体積に応じて一定の圧力が保たれています。
不凍液が微量でも漏れていると、配管内の総液量が減少します。
液量が減ると、それに比例して内部の圧力も下がります。
「最近、暖まりが悪い」「設定温度に達しない」などの症状と併発している場合は、特に注意が必要です。
また、システム自体が壊れていなくても、圧力計がセンサーが壊れていると、圧力数値は正確に表示されません。
「暖まりに問題はないが、数値の動きがおかしい」という症状の場合は、圧力計やセンサーの故障の可能性もあります。
※圧力計は劣化しやすい部品ですが、システム自体に影響ない場合、お客様のご判断で圧力計は修理せずそのままお使いになるケースもあります。
自己判断せず、信頼できる専門業者に相談を
圧力の異常は、思わぬ故障や事故につながるリスクをはらんでいます。
膨張タンクの不具合や不凍液漏れなどは、一見すると軽微に見えるかもしれません。
しかし、放置すれば配管の破裂や暖房機能の停止といった重大トラブルを引き起こす恐れがあります。
特に以下のような状態が見られる場合は、すぐに専門業者へ相談することをおすすめします。
- 圧力が急に上がる、あるいは上がり続ける
- 圧力がまったく上がらない
- 圧力が徐々に下がっていく
- 安全弁から液が噴き出している
- 圧力計の動きが不自然
- 室温が上がらず、暖まりが悪い
これらのサインは、膨張タンク、圧力センサーなどの異常の初期症状である可能性があります。
問題を早期に発見し、コストを最小限に抑えるためにも、無理な自己修理は避けてください。
お使いのボイラー設備に少しでも違和感を覚えたら、地元で実績のある専門業者へ、まずは点検のお問い合わせを。
当社は、機種や使用環境に応じた無料相談をお受けしています。