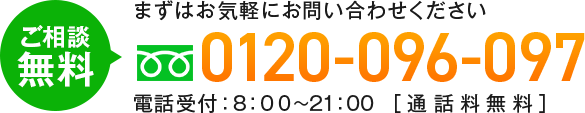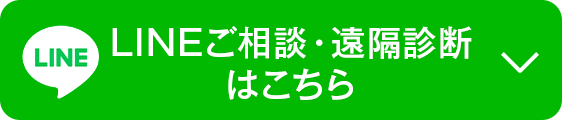暖房ボイラー密閉式の圧力低下ガイド|エア抜き・不凍液補充・応急処置の実務
暖房ボイラーの圧力計が普段より低い値を示している。
パネルヒーターや床暖房の一部が冷えている。
本記事は、そんなときに現場でできる初期確認のポイントを解説しています。
暖房が効かない、などの症状は、密閉式暖房ボイラーの圧力低下が原因となっていることが少なくありません。
圧力低下は放置すると暖房停止や設備損傷につながりかねず、宿泊施設や介護施設の運営リスクになります。
今回は、現場でできる応急処置から業者依頼の目安まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
圧力低下に気づく初期症状とサイン
密閉式暖房ボイラーの圧力低下は、まず現場での「異変」として感じることが多いです。
以下のような症状に気づいたときは、圧力低下を疑ってみましょう。
パネルヒーターや床暖房の一部が冷たい
特定の場所や部屋の一角が暖まらないのは、温水の循環が十分でないサインです。
圧力低下が起こると、温水が末端まで届かず、熱交換がうまく行われないことがあります。
暖房全体の効きが悪い
設定温度通りに室温が上がらず、いつもより時間がかかる場合も、圧力低下のおそれがあります。
圧力が低下すると、温水が安定して循環しないため、暖房の効きが悪くなります。
ポンプの異音・振動が発生する
「シュルシュル」「うなり音」などの異音や、ポンプの振動は、空転やエア噛みの兆候です。
空転とは、本来水を吸い込んで押し出す役割を持つポンプが、何らかの理由で水をうまく吸い上げられず、空気だけを回し続けてしまう状態を指します。
エア噛みとは、配管やボイラーの回路内に空気が入り込み、その空気が水や不凍液の流れを妨げる現象です。
空転やエア噛みが起こると、圧力低下の原因になります。
操作パネルのエラー表示
循環不良を示すエラーコードが出ている場合、圧力低下が起きている可能性があります。
症状が現れたときの初期確認ポイント
初期症状のサインを認識した場合には、まず次のポイントを確認しましょう。
圧力計の数値確認
圧力計は密閉式ボイラーの運転状態を示す重要な指標です。
通常は0.3〜0.5 MPa前後が正常範囲です。
しかし、これを大きく下回る場合(例:0.1 MPa以下)は異常値と考えられ、圧力低下を疑います。
圧力計の場所は、施設で導入されているシステムによって異なります。
一般的には次の場所を確認することが多いです。
- ボイラー出入口の圧力計(アナログ)
- または膨張タンク・安全弁に近い回路圧力計(アナログ)
- または制御盤の圧力表示(電子圧力計の値)
操作パネルの警告やエラー履歴
異常停止やエラーコードが出ていないか確認します。
例えば、一部の密閉式システムでは、パネルに「圧力スイッチ異常」「センサ断線」といったメッセージ表示が出ることがあります。
また「E8:圧力異常」や「P22:循環ポンプ低流量」などのエラーコードつきで異常を知らせる表示が出ていることもあります。
これらの表示が出ていれば、圧力スイッチの誤作動や循環不良の可能性が高く、圧力低下が疑われます。
これらの履歴を記録しておくことで、後々、原因の特定に役立つことがあります。
水漏れ・補水履歴の確認
密閉式暖房システムは、温水や不凍液を、密閉配管内で一定の圧力で循環させています。
密閉された回路のなかで循環させるので、通常、温水や不凍液が失われることはありません。
しかし、それでも、長期間の運転でわずかに水や不凍液が失われることがあります。
(理由は、配管の微細な漏れや膨張タンクの不良など様々です)
まずは水漏れ(または不凍液の漏れ)がないか、配管や機器の周辺を目視で確認しましょう。
また、もし記録が手元にある方は、補水履歴も念のためチェックしてみると良いでしょう。
日常業務で補水を意識したことがない場合は、何のことか分からないかもしれませんが、通常は、定期点検などで外部業者が補水を行っていることがあります。
補水は、失われた分を補って回路圧力を正常値に戻す役割を持っています。
もし、過去の補水記録や業者の対応履歴があれば、確認してみましょう。
短期間に何度も補水していた場合、どこかに異常が隠れているかもしれません。
暖房の温度ムラや、ポンプの異音
初期症状でも示しましたが、暖房の温度ムラがあれば循環不良のサインです。
またポンプの異音や振動は、ポンプの空転やエア噛みの可能性を示しています。
「シュルシュル」「うなり音」などの異音や、ポンプの振動がないか、確認しましょう。
機器の安全停止、および業者へ連絡
異音・異臭・強い振動がある場合は、操作パネルの「停止」ボタンで暖房ボイラーを停止しましょう。
無理に運転を継続すれば、事故リスクを高め、機器の損傷を広げる可能性があります。
そして確認した数値・症状・操作履歴を簡潔にまとめ、すぐに業者に連絡しましょう。
業者へは、以下のように具体的に伝えることがポイントです。
- 「圧力計は0.1 MPa」
- 「パネル右半分が冷たい」
- 「操作パネルにエラーP22」
圧力低下は、エアの混入や、不凍液の漏れが原因となっていることがあります。
そのため、現場では実務上、原因を特定した上で、エア抜きや不凍液の補充(補水)などを行うことがあります。
密閉式暖房ボイラーのエア抜き実務
圧力低下の背景には、空気混入による循環不良(エア噛み)が関わっていることがよくあります。
エア抜きは、回路内の空気を抜き、正常な循環を取り戻す作業です。
※エア抜きは点検時にプロの業者が行う作業です。
エア抜きの必要性
空気が混入すると温水の流れが途絶え、パネルヒーターや床暖房に熱が届かず、ポンプに負荷がかかります。
結果として圧力低下やさらなる設備不良を招きます。
正しいエア抜き手順
- ボイラーと配管が十分に冷めていることを確認します。
- エア抜きバルブの位置を確認し、下に受け皿を置きます。
- バルブを少しずつ開き、空気が抜けて温水が出たら閉めます。
- 圧力計を確認し、0.3〜0.5 MPa前後で安定していることを確認します。
注意点
急にバルブを開けると熱湯飛散で火傷の恐れがあります。
操作はゆっくり、慎重に行い、作業後は忘れずに圧力の再確認と異音確認をします。
不凍液・補水の補充実務
不凍液や補水は、漏れや長期使用で減少した場合に必要です。
圧力低下が続く場合、応急補充を行います。
※補水は点検時にプロの業者が行う作業です。
不凍液の役割
低温環境での凍結防止と、配管・機器の保護を担います。
不足すると循環が不安定になり、圧力低下やトラブルの原因に。
不凍液の補充(補水)の流れ
- 使用する不凍液の種類・希釈比率を確認(取扱説明書を参照)。
- 補水口からゆっくりと補充。急ぐと空気を巻き込みます。
- 圧力計を確認し、0.3〜0.5 MPa前後で安定するまで調整。
- 最後に漏れや異音がないか点検します。
注意点
補水や補充を繰り返す場合は漏れや機器不良が潜んでいることが多いです。
そのため、通常は応急処置のみで済まさず、機器の劣化や故障も視野に入れて点検します。
エア抜きや不凍液の補充はプロに任せるべき
密閉式暖房システムは高温・高圧で運転されています。
エア抜きや補水は正しい手順や順序、適切な圧力確認が必要で、誤った操作は危険を伴います。
- 高温・高圧の温水や不凍液が飛散し火傷や機器損傷の危険
- 空気の再混入や過圧状態を引き起こし、さらなる異常を招く
- 膨張タンク・安全弁・圧力調整系統に誤った負荷をかけてしまう
補水やエア抜きはプロの業者が圧力状態・温度状態を確認した上で、安全な手順で行うべき作業です。
機器の扱いに不慣れな場合は、自分で何とかしようとするのはやめましょう。
異常のサインを察知したら、必要な記録を残し、正確に業者に状況を伝えることが大切です。
業者依頼の目安|こんなときは迷わず相談を
密閉式暖房ボイラーの圧力低下は、「この程度なら様子を見ていいのか、それとも業者に連絡すべきか」の判断に迷うことがあります。
特に小規模施設では、パネルの一部が冷たいだけなら「運営に大きな支障はないし、しばらく様子を見よう」と感じる方も多いでしょう。
しかし、次のような異変が見られたときは、迷わず業者に相談することをおすすめします。
- 圧力計の値が短時間でさらに下がり続けている場合
- ポンプやボイラーからの異音・振動が続いている場合
- 異臭(焦げ臭など)がする場合
- 暖房の効きが急に悪化し、室内が十分に暖まらない場合
こうした異変を放置すると、暖房が完全に止まる、宿泊客や利用者に不便をかける、さらには大掛かりな修理・機器交換が必要になるなど、施設運営全体へのリスクに直結します。
さらに、修理が必要な場合も、すぐに部品が手に入るとは限りませんので、迷ったときは「念のため相談する」気持ちで、早めに業者に連絡することが大切です。
結果的に、全体の運営に支障をきたすことなく、安全でコスト負担も抑える対応が可能になります。
当社は密閉式暖房ボイラーの圧力低下診断、現場エア抜き・不凍液補充、点検作業を承っています。
初期診断は無料です。ぜひご相談ください。